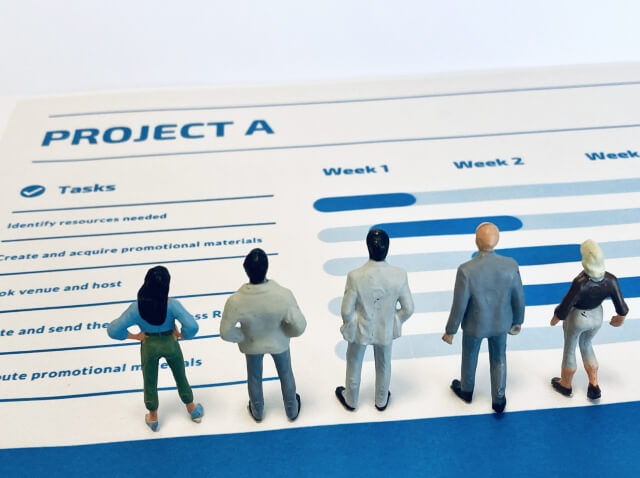建設コンサルタントとは
建設コンサルタントとは、社会資本整備に関する幅広い知識と技術を活かし、道路や橋梁、河川、上下水道などのインフラ整備において調査・設計・監理を行う専門家を指します。建設コンサルタントの役割は単に「設計図を描く」ことにとどまらず、地域社会の安全性や利便性を高めるために、長期的な視点から計画を立案し、最適な解決策を提示することです。特に災害が多い日本では、防災・減災の観点から建設コンサルタントの存在が不可欠であり、社会基盤を守る縁の下の力持ちといえます。
また、建設コンサルタントは「技術士」などの国家資格を持つ専門家が多く、専門性を背景に自治体や官公庁、民間企業からの依頼に応えます。単なる建設工事ではなく「将来を見据えた持続可能なまちづくり」に貢献する仕事です。
主な業務内容(設計、計画、調査、監理など)
建設コンサルタントの業務は多岐にわたります。代表的なものは以下の通りです。
- 調査業務
現地の地質・地形、交通量、環境影響などを調査し、基礎データを収集します。例えば道路整備では、交通需要や周辺環境への影響を調べることが不可欠です。
- 計画業務
調査結果をもとに、将来的な需要や地域の特性を踏まえた最適なインフラ計画を策定します。都市計画や防災計画も含まれ、地域社会に直結する業務です。
- 設計業務
具体的な設計図を作成し、施工に必要な詳細な仕様を決定します。橋梁やトンネル、上下水道など、構造物ごとに高度な専門知識が求められます。
- 監理業務
施工段階では、工事が設計通りに進んでいるか、安全性や品質に問題がないかを監理します。工事業者と発注者をつなぐ立場として、中立かつ専門的な判断が必要とされます。
これらの業務は個別に独立しているのではなく、一連のプロセスとして密接に関わり合っています。例えば、調査段階で得られたデータが設計や監理の品質に大きく影響するため、各工程の正確さと専門性が最終的な成果物の質を決定づけます。
公共事業や民間プロジェクトでの重要性
建設コンサルタントが活躍する舞台は、公共事業と民間プロジェクトの両方に広がっています。
まず公共事業においては、国や自治体が発注する道路整備、河川改修、ダム建設などに関わります。特に近年は地震や豪雨災害への対応が求められ、防災・減災に直結する業務が増加しています。国土交通省も「建設コンサルタントは公共事業における技術的支援の中核的存在である」と位置付けており、その社会的責任は非常に大きいと言えます。
一方で民間プロジェクトでも、再開発事業や大規模商業施設の建設などで建設コンサルタントが活躍しています。企業の事業戦略に直結するため、コスト管理や環境配慮など多面的な視点が求められます。特に最近は「カーボンニュートラル」や「SDGs」への取り組みが重視されており、建設コンサルタントには環境に配慮した設計や持続可能性を確保するための技術提案が期待されています。
公共・民間を問わず、建設コンサルタントは社会の基盤整備を担い、生活の安全や利便性を支える重要な存在です。求人市場でも安定した需要があり、将来性のある専門職として注目されています。
建設コンサルタントの平均年収
建設コンサルタントの平均年収ですが、厚生労働省のjobtagでは、建設コンサルタントに一番近い職種である「土木設計技術者」「建築設計技術者」で調べてみると、それぞれ596.5万円、641.6万円となっています。また転職会議では490万円と紹介されています。
参考:厚生労働省jobtag
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/22,https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/20
転職会議:https://jobtalk.jp/salary_matome/jobs/144?age_min=25&age_max=30
その他転職情報サイトではそれぞれ若干のばらつきはあるものの、平均年収は498万円~632万円と紹介されています。日本の給与所得者の平均年収が450万円前後であることを考えると、建設コンサルタントは総じて高い給与水準にある専門職であることがわかります。
年齢・経験別の年収目安
建設コンサルタントの年収は、他の多くの職種と同様に、年齢と経験年数に比例して上昇していく傾向が顕著です。若手のうちは先輩技術者の指導のもとで経験を積む期間となり、年収も日本の平均と近いか少し高いくらいからスタートします。
具体的な年齢別の年収目安を見てみましょう。
- 20代: 約370万円~450万円
- 30代: 約420万円~550万円
- 40代: 約500万円~650万円
- 50代: 約550万円~700万円以上
30代になると一人前の技術者としてプロジェクトの中核を担うようになり、年収も大きく上昇します。特に、建設コンサルタント業務に必須ともいえる「技術士」などの難関国家資格を取得すると、資格手当が付くだけでなく、管理技術者としてより責任のある立場を任されるため、さらなる年収アップが期待できます。40代から50代にかけては、プロジェクトマネージャーや管理職として部下を育成する立場となり、年収もピークを迎えます。企業によっては、40代で900万円以上、50代で1,000万円を超えるケースもあり、経験と実績を積み重ねることで着実に高収入させるのがこの仕事の大きな魅力です。
参考: https://shukatsu-mirai.com/archives/68691
https://job-q.me/articles/5583
https://kenconblog.com/553/
勤務地や地域による年収の差
勤務地も年収を左右する重要な要素です。地域別の平均年収を見てみると、以下のような序列が見られます。
- 関東: 約700万円
- 中部・近畿: 約650万円
- 中国: 約620万円
- 北陸: 約600万円
- 四国: 約580万円
- 北海道・東北・九州: 約570万円
上記の通り、東京を中心とする関東地方が突出して高い水準にあります。これは、大手企業の多くが本社を構えていることに加え、国家的な大規模プロジェクトが集中しているためです。また、物価や家賃といった生活コストが高いことも給与水準に反映されています。
一方、地方都市では年収が首都圏に比べて低くなる傾向がありますが、その分、生活コストを抑えられるというメリットもあります。近年はリモートワークの導入や地方創生に関連する公共事業の増加もあり、地方で働きながらも高い専門性を活かせる機会が増えています。転職を考える際には、希望する年収だけでなく、自身のライフプランや働き方に合わせて勤務地を選択することが重要です。
引用元: https://beavers.co.jp/blog/5951/
年収に影響する要素
建設コンサルタントの年収は、個人のスキルや経験、企業の特徴、資格の有無、担当する業務の内容など、さまざまな要素によって大きく左右されます。ここでは「経験年数・専門分野」「所属企業の規模や事業内容」「資格の有無」「担当業務やプロジェクト規模」という4つの観点から詳しく解説します。
経験年数・専門分野による変動
建設コンサルタントは、インフラ整備や都市計画、環境分野など幅広い業務に携わる職種です。経験年数が増えるほど専門性が高まり、プロジェクト全体を統括する立場に立つ機会が増えるため、年収は大きく上昇する傾向があります。また、どの専門分野を選ぶかも将来の年収に影響を与えます。建設コンサルタントの業務は、河川、道路、橋梁、トンネル、都市計画、環境、情報(GIS)など非常に多岐にわたります。例えば、近年需要が高まっている防災・減災、インフラの維持管理・アセットマネジメント、あるいはDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した設計などは、将来性が高く、専門性を高めることで高い報酬を得られる可能性があります。自身の興味関心と社会のニーズが合致する分野を見極め、専門性を磨き続けることが、長期的なキャリア形成と年収アップに繋がります。
所属企業の規模や事業内容
所属する企業の規模や事業内容は、年収に最も直接的な影響を与える要素の一つです。一般的に、業界大手の総合建設コンサルタントは、大規模で社会的に影響力の大きいプロジェクトを数多く手がけており、それに伴って年収水準も高く設定されています。スーパーゼネコンのグループ会社や、独立系の大手企業では、30代で年収700万円以上、管理職クラスになれば1,000万円を超えることも珍しくありません。
一方で、特定の分野に特化した専門コンサルタントや、地域に根差した中堅・中小企業も数多く存在します。これらの企業は、大手ほどの給与水準ではないかもしれませんが、特定の技術で高いシェアを誇っていたり、ワークライフバランスを重視した働き方ができたりと、独自の魅力を持っています。また、大手に比べて業務の幅が広い傾向があり、早期から実践経験を積める機会が多いという魅力もあります。
近年では建設業界のDX化を推進するITベンチャーや、外資系のコンサルティングファームも建設分野に参入しており、従来とは異なる給与体系やキャリアパスを提供しています。企業の事業内容や安定性、将来性、そして社風などを総合的に判断し、自身の価値観に合った企業を選ぶことが重要です。
資格(技術士、RCCMなど)の有無
建設コンサルタントとしてキャリアアップと年収向上を目指す上で、専門資格の取得は極めて重要です。特に、技術部門の最高峰の国家資格である「技術士」と、建設コンサルタント業務の責任者として認められる「RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)」は、年収に大きな影響を与える二大資格です。
これらの資格を持つ技術者は、公共事業の入札条件である「管理技術者」や「照査技術者」として配置されるため、企業にとって不可欠な存在です。そのため、多くの企業では、これらの資格取得者に対して月々数万円の資格手当を支給しています。例えば、技術士であれば月3万円~10万円、RCCMであれば月1万円~3万円程度が相場とされています。これは年収に換算すると数十万円単位のプラスとなり、基本給の上昇とは別に収入を底上げする大きな要因となります。資格は、自身の技術力を客観的に証明するだけでなく、会社への貢献度をアピールし、より責任ある立場と高い報酬を得るための強力な武器となるのです。
担当業務やプロジェクト規模の違い
建設コンサルタントの年収は、担当する業務内容やプロジェクトの規模によっても左右されます。例えば、設計や計画の初期段階を担当する場合と、現場管理やプロジェクト全体のマネジメントを担う場合では、求められる責任やスキルが異なり、その分給与にも差が出ます。
大規模プロジェクトや公共インフラ関連業務では、予算規模が大きく、業務の責任も重大なため、担当者の評価や報酬も高くなる傾向があります。一方、地方の小規模案件や特定分野に限定された業務では、年収の上昇幅は比較的緩やかです。
特に転職を検討している人にとっては、「どの分野に強みを持つか」「どの規模のプロジェクトに関わりたいか」を明確にすることで、自身のキャリアと年収の両面で納得できる選択が可能になります。
給与体系と待遇
建設コンサルタントの給与体系や待遇は、転職を検討する際に必ず確認しておきたい重要なポイントです。年収を構成する要素には、基本給や賞与、資格や現場に応じた手当、さらに福利厚生や労働環境の違いがあり、これらは企業ごとに大きな差があります。
基本給・賞与の仕組み
建設コンサルタントの給与体系は、一般的に基本給と賞与から成り立っています。賞与は年2回支給されるのが一般的です。大手企業の場合、賞与の支給額が年収全体に占める割合は大きく、年間で基本給の4〜6か月分に相当するケースもあります。一方、中小企業では賞与の支給額は控えめで、基本給を中心とした給与体系が多い傾向にあります。求人票を確認すると、賞与を含めたモデル年収として「400〜600万円程度」が記載されるケースが一般的であり、大手企業では「700〜900万円以上」を提示する例も見られます。
資格手当・現場手当などの各種手当
建設コンサルタントにとって、資格の有無は給与に直結します。特に「技術士」や「RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)」の資格は評価が高く、多くの企業が資格手当を設けています。例えば技術士を保有している場合、月額3〜10万円、年間で数十万円の手当が支給されるケースが一般的です。
また、現場勤務が多い技術者には「現場手当」や「出張手当」が支給される場合があります。大規模インフラ工事や災害復旧などのプロジェクトに従事する際には、拘束時間や移動の負担が大きいため、企業は手当で労働環境を補っています。さらに、役職手当や家族手当なども給与に加わることで、年収の総額に差が生じます。
こうした手当は企業ごとに大きく異なりますので、求人情報を確認する際は「資格手当の有無」「現場手当の支給条件」などを具体的に確認することが重要です。
福利厚生や労働環境の特徴
給与に加えて、福利厚生や労働環境も待遇を判断するうえで大切な要素です。大手建設コンサルタント企業では、住宅手当や退職金制度、確定拠出年金などの福利厚生が整っていることが多く、安定した就労環境を提供しています。また、近年は働き方改革の影響で、リモートワークやフレックスタイム制度を導入する企業も増えており、ワークライフバランスを重視する人にとって魅力的なポイントとなっています。
一方、中小規模の企業では福利厚生が限定的な場合もありますが、地域密着型で転勤が少なく、地元で腰を据えて働けるというメリットがあります。特に家庭との両立を重視する人にとっては、こうした労働環境が適しているケースも多いです。
また、労働環境の観点では「労働時間」も重要です。国土交通省の発注する公共事業が多い建設コンサルタント業界では、年度末に業務が集中しやすく、繁忙期には残業が増える傾向があります。しかし、近年はICTの導入や業務効率化の取り組みにより、過重労働を改善しようとする動きも強まっています。
高年収を目指す方法
上記でもご紹介している通り、建設コンサルタント業界では、資格が給与や昇進に直結します。特に「技術士」は国家資格の中でも最高峰とされ、資格保有者には資格手当や昇格の優遇があり、年収が数十万円〜100万円以上上がるケースもあります。建設コンサルタントにおいて年収アップに直結しやすい資格は下記の通りです。
- 技術士
- RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)
- 測量士・地質調査技士
- 施工管理技士(1級土木施工管理技士など)
さらに、専門分野に特化したスキル強化も高収入につながります。都市計画、防災、環境保全、再生可能エネルギーなど、社会的需要の高い領域で専門性を磨けば、大規模プロジェクトや官公庁案件に携わる機会が増え、結果として高収入を得やすくなります。特に近年は気候変動対策やインフラ老朽化対策に注目が集まっており、これらの分野の専門知識を持つ人材は市場価値が高いといえます。
年収の高い企業・求人の特徴
転職活動で年収を重視するなら、企業や求人の特徴を見極めることが重要です。
大規模プロジェクトを扱う能力がある大手建設コンサルタントや、橋梁、道路、トンネルなどのインフラ設計・管理といった高度な技術力が必要とされる案件にも対応可能な専門性の高い企業は、給与水準や待遇が安定しており、平均年収も高い傾向にあります。
例えば、転職情報サイトにおいて、建設コンサルタント業界年収ランキング上位企業としてたびたび紹介されている建設技術研究所の平均年収は995万円、NJSは829万円(2024年12月31日現在)となっており、非常に高いことが分かります。
参考:各社有価証券報告書https://www.ctie.co.jp/ir/financial/yuho/uploads/2025/03/62_all.pdf
https://data.swcms.net/file/njs/dam/jcr:38adde41-b6b0-4314-8319-5433aac01995/S100VHUQ.pdf
また、海外プロジェクトやインフラ輸出に関わる企業は、英語力や国際経験が求められる一方で、高い報酬が期待できます。さらに、ICTやBIM/CIMといった最新技術を活用する企業も、付加価値の高い業務を担うことから給与水準が高めです。転職の際は、求人票に記載された「年収レンジ」や「資格手当の有無」、企業のプロジェクト内容に注目することがポイントです。
成果を活かした転職戦略
年収を高めるもう一つの方法は、自身の成果を明確にアピールすることです。建設コンサルタントの仕事は「どのようなプロジェクトに関わり、どんな成果を出したか」が重視されます。たとえば、インフラ設計において工期短縮やコスト削減を実現した実績、大規模案件でチームを率いた経験などは、転職市場での評価を高めます。
特に30代後半以降は、プロジェクトマネジメント能力や人材育成スキルなど「リーダーシップの経験」が重視され、これを武器にすれば年収アップにつながる可能性が高まります。逆に、20代であれば「資格取得や専門スキルの習得」を武器にポテンシャルを示すことが効果的です。
さらに、転職エージェントを活用することで、アピールポイントのアドバイスや非公開求人の情報、年収交渉のサポートなどを受けられる点も大きなメリットです。
転職市場の動向
建設コンサルタント業界は、社会インフラの整備や維持管理を支える重要な分野であり、常に一定の需要があります。特に近年は、インフラ老朽化対策や自然災害への対応、環境配慮型プロジェクトの増加などを背景に、求人市場が活発化しています。
建設コンサルタントの求人傾向
建設コンサルタントの求人は、官公庁や自治体からの公共事業発注に依存する部分が大きいため、年度末や大型予算の成立時期に多くなる傾向があります。dodaの転職求人倍率レポート(2025年7月)によると建設業界の求人倍率は4.90となっており、全業界の中でも高水準を維持しています。
参考:https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/
求人内容としては、設計・調査・計画業務を担うポジションが多く、特に都市計画、防災関連、環境分野の需要が増加しています。また、ICTやBIM/CIMを活用した案件も増えており、デジタル技術に対応できる人材のニーズが高まっているのも特徴です。
中途採用で求められる経験やスキル
中途採用では、即戦力としてのスキルや経験が重視されます。具体的には、土木設計や構造解析の実務経験、プロジェクトマネジメントの実績、発注者との折衝経験などが評価されます。特に、技術士やRCCMの資格を持つ人材はプロジェクトの中核を担えるため、採用時に優遇されるケースが多いです。
また、コミュニケーション能力や調整力も重要視されます。建設コンサルタントは多様なステークホルダー(官公庁、ゼネコン、地域住民など)との調整業務が多いため、単に技術力だけでなく、円滑にプロジェクトを進める能力が求められます。さらに、環境配慮型設計やICT活用の知見を持つ人材は、最新ニーズに対応できる点で市場価値が高いといえるでしょう。
未経験者が転職を成功させるポイント
未経験から建設コンサルタントを目指す場合、即戦力性が不足するため工夫が必要です。ポイントの一つは「関連分野の経験をアピールすること」です。たとえば、施工管理や測量、CADオペレーションの経験がある場合、それらのスキルはコンサルタント業務に応用できるため評価されやすいです。
また、資格取得に挑戦することも効果的です。RCCMや土木施工管理技士などの資格を持つことで、基礎的な知識と実務理解を示せます。さらに、BIM/CIMやGISといったデジタル技術のスキルを独学で習得していることも大きな強みになります。
未経験者が転職を成功させるもう一つのポイントは「ポテンシャルと意欲を具体的に示すこと」です。求人票には「未経験歓迎」と記載される案件も一定数ありますが、そこでは新しい知識を吸収し、長期的に成長できる姿勢が評価されます。面接では「なぜ建設コンサルタントを目指すのか」「将来的にどんな専門分野で貢献したいのか」を明確に語ることが重要です。
このように、建設コンサルタントの転職市場は安定した需要があり、中途採用では専門性や経験が重視されます。一方で未経験者にも挑戦の余地はあり、資格取得やスキル習得、意欲的な姿勢を武器にすれば、転職を成功させるチャンスは十分に存在します。
まとめ
上記の通り、建設コンサルタントは経験や資格、企業規模によって年収は大きく変動します。特に大手企業や資格保有者は高収入を得やすい傾向にあり、年収アップのためには資格取得、専門スキル習得、成果の可視化が重要です。年収を重視した転職活動の場合には、大手企業や資格手当が充実した企業を狙うと有利になるでしょう。
一方で年収だけでなく、長期的な目線を持ち、得られるスキルやキャリアパスなどの観点で考えることも重要なポイントです。
また労働時間や残業の多さ、ワークライフバランスも企業によって差があるため注意が必要です。待遇面だけでなく、働きやすさや将来性を含めた総合的な判断が求められます。