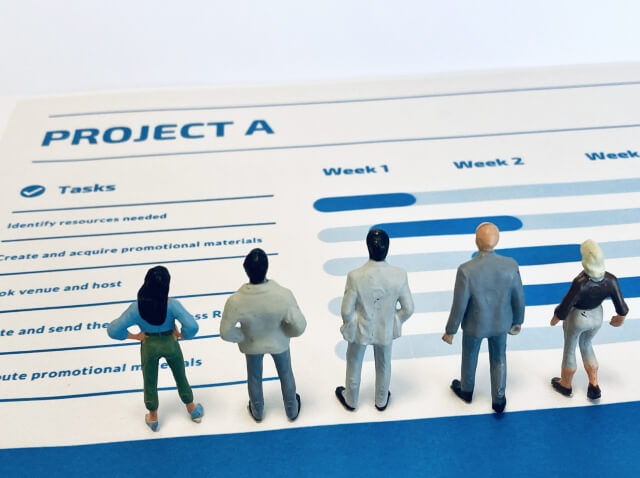管理職の給料とは?
管理職と一口に言っても、その役職や業界、企業規模によって給料は大きく異なります。まずは管理職という立場の基本的な役割や、一般社員との給与の違いを整理し、給料に影響を与える主な要素を確認していきましょう。
管理職とはどんな役職?
管理職は、組織の中で人や業務を統括し、成果責任を担う役割を持ちます。具体的には課長・部長・部門長などが該当し、部下のマネジメントや業績管理、戦略実行を任されます。単に業務を遂行するだけでなく、組織全体の方向性を示し、成果を生み出すことが求められるのが特徴です。
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」では、「役職」の定義として、
| 一般労働者のうち、雇用期間の定めのない者について、役職者を「部長級」、「課長級」、「係長 級」等の階級に区分し、役職者以外の者を「非役職者」 |
と定めています。
しかし、管理職は法律によって明確に定義されているわけではありません。外資系企業では「ディレクター」「マネージャー」などと呼ばれるなど企業によって管理職の定義や役職名、業務や責任の範囲は様々です。
日系企業でも外資系でも主に管理職は「監督者」を意味し、経験や社歴が比較的浅い従業員を監督する、管理職の管理をする者も上級管理職という監督者となります。
他に、業務やプロジェクトを管理する管理職など業務内容も多岐にわたります。
参照元:マネージャーとディレクターの違いとは?外資系企業の役職を紹介 | Indeed (インディード)(2025年4月)
一般社員との給料の違い
厚生労働省「令和4年 賃金構造基本統計調査」によると、非役職者(一般社員)の平均月給は約28.1万円であるのに対し、課長級は約48.7万円、部長級は約58.6万円となっています。つまり、管理職は一般社員よりも月給ベースで1.5倍〜2倍近い差がつくことが多いのです。
さらに、最新の「令和6年 賃金構造基本統計調査」の結果では、より鮮明な格差が浮き彫りになっています。
- 部長級:平均月給 627,200円 → 非役職者(302,800円)の 約2.07倍
- 課長級:平均月給 512,000円 → 非役職者の 約1.69倍
- 係長級:平均月給 385,900円 → 非役職者の 約1.27倍
また、性別でも格差が存在し、管理職階級になるほど拡大傾向にあります。
-
- 男性:部長級636,400円/課長級522,400円/非役職者325,600円
- 女性:部長級549,900円/課長級458,100円/非役職者270,300円
→ 男性部長級と比べ、女性部長級は約8.6万円少ないなどの差が顕著です。
まとめて整理すると:
| 役職 |
平均月給(令和6年) |
非役職者比 |
| 非役職者 |
約302,800円 |
— |
| 係長級 |
約385,900円 |
約1.27倍 |
| 課長級 |
約512,000円 |
約1.69倍 |
| 部長級 |
約627,200円 |
約2.07倍 |
また、管理職層の中でも性別による賃金格差が一定幅で存在することは見逃せません。
給料に影響する要素
管理職の給料は、一律に決まるものではなく、さまざまな要因によって大きく左右されます。特に影響が大きいのは「業界」「企業規模」「役職の違い」です。
業界
収益性や専門性の高い業界では、管理職の給与水準も高くなる傾向があります。たとえば厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、金融業や情報通信業は全体的に給与水準が高く、管理職においてもその傾向は顕著です。一方で、宿泊業や飲食サービス業などは給与水準が低めで、管理職でも年収格差が大きく出やすいのが現実です。
企業規模
従業員規模による給与差も明確です。調査結果では、1,000人以上の大企業に勤める課長級は平均50万円台後半の月収であるのに対し、100〜999人規模では40万円台後半、100人未満では40万円を切るケースもあるとされています。企業規模が大きいほど利益水準も高く、役職に応じた給与も相対的に高くなるのです。
役職の違い
同じ管理職でも、肩書きによって給与差は大きく広がります。係長級から課長級に昇進する際に年収が100万円以上上がるケースも珍しくなく、さらに部長級、部門長へと昇進すれば、非役職者の倍以上の給与水準に達することもあります。責任範囲が拡大し、経営への関与度が高まるほど、給与水準も連動して上がる仕組みです。
このように、業界・企業規模・役職といった要因を総合的に見なければ、自分の給与が「高いのか低いのか」を正しく判断することはできません。
参照元:管理職の平均年収はどのくらい?業界別の管理職年収の特徴 – KOTORA JOURNAL(2025年7月)
管理職の年収と給料の実態
管理職といっても、役職や業界によって年収には大きな差があります。ここでは厚生労働省の統計をもとに、管理職の平均年収や業界別・企業別の給与水準を具体的に見ていきましょう。
管理職の平均年収とその範囲
役職ごとの平均を概算すると以下の通りです(厚労省統計をもとに試算)。
| 役職 |
平均月給 |
推定年収(賞与含まず) |
| 部長級 |
約58.6万円 |
約703万円 |
| 課長級 |
約48.7万円 |
約584万円 |
| 係長級 |
約36.9万円 |
約443万円 |
| 一般社員 |
約28.1万円 |
約338万円 |
つまり、部長級と一般社員では年収で500万円程度の差が生じることもあり、管理職になることが収入面での大きなステップアップにつながることがわかります。
また、給与水準には「企業規模」による差も顕著です。従業員1,000人以上の大企業に勤める部長級は、年収1,000万円を超えるケースが少なくありません。一方、中小企業では部長級であっても年収600〜700万円程度にとどまることも多く、同じ役職でも働く環境によって年収レンジが大きく異なる点には注意が必要です。
さらに、調査では年齢層別の差も確認できます。40代後半から50代前半が管理職給与のピークとなり、その後は昇進機会や定年再雇用の影響で伸びが緩やかになります。
このように、「管理職」と一口に言っても、年収の範囲はおよそ 500万円台〜1,000万円超と広く、業界・企業規模・役職・年齢といった複数の要素が組み合わさって決まるのが実態です。
業界別管理職年収ランキング(例:IT、製造業、商社など)
同調査では業界差も顕著です。
- 電気・ガス・水道業:402万円
- 学術研究・専門技術サービス業:385.5万円
- 情報通信業:378.8万円
- 宿泊・飲食サービス業:257.4万円
インフラや専門性の高い業界が上位に、サービス業は低めに出ています。
企業別の管理職給与比較
管理職の給与は、同じ役職でも企業の規模や業種によって大きな差があります。厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」によると、従業員規模が大きい企業ほど管理職給与が高いという傾向が明確に表れています。
| 企業規模 |
課長級 年収目安 |
部長級 年収目安 |
| 従業員1,000人以上(大企業) |
約850万〜900万円 |
1,000万円超が一般的 |
| 従業員100〜999人(中堅企業) |
約700万円 |
約700万〜900万円 |
| 従業員10〜99人(中小企業) |
約600万円弱 |
約600万円台にとどまる |
さらに、企業ごとの「給与テーブル」や「評価制度」も影響します。たとえば外資系企業や大手商社は成果主義が強く、業績次第で大幅な年収アップが期待できる一方、国内の伝統的な企業では年功序列の要素が残り、昇進や給与水準が安定している代わりに伸び幅は限定的です。
このように、管理職の給与を比較する際は「役職名」だけでなく、企業規模・業種・人事制度の違いまで考慮することが、現実的な年収イメージを掴む上で欠かせません。
参照元:厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査の概況 (2025年3月)
管理職の給料に影響を与える要素
同じ「管理職」でも、課長と部長では給与に大きな差があり、さらに企業規模や業績によっても年収水準は変わります。
給与は役職の肩書きだけで決まるものではなく、組織の大きさや責任範囲、担当する部下の人数など複数の要素が関わっています。ここでは、管理職の給料を左右する主な要因について詳しく見ていきましょう。
役職と給与の関係
課長→部長→部門長と上がるごとに給与も上昇。部長クラスでは非役職者の約2倍以上になる水準です。
課長から部長へ昇進することで年収が約200万円増加するケースも少なくありません。特に部長クラスでは、一般社員の2倍以上の給与水準となり、役職の重みが給与に強く反映されていることがわかります。
さらに企業によっては「部門長」や「事業部長」といった役職が存在し、このクラスになると年収1,200万円以上に達することもあります。こうしたポジションは経営に近い立場であり、組織全体の成果責任を担うため、報酬もそれに比例して高くなるのです。
ただし、役職が上がるほど給与も上がる一方で、責任範囲は飛躍的に広がります。課長は「チーム単位の成果」、部長は「部門単位の成果」、部門長は「会社全体の事業成長」と、管理するスケールが拡大するため、プレッシャーや求められるスキルも比例して高まる点には留意が必要です。
組織規模と業績による給与差
管理職の給与水準は、所属する企業の規模や業績によって大きく変わります。厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」でも、従業員規模が大きい企業ほど管理職の平均給与が高いことが明らかになっています。例えば課長級の平均月給は、従業員1,000人以上の大企業では約56万円ですが、100人未満の中小企業では約41万円と、月給で15万円以上、年間で200万円以上の差が生じています。
さらに、企業の業績による影響も無視できません。大企業であっても業績が低迷していると賞与が減少し、結果的に年収は大きく下がります。一方、業績が好調な企業や利益率の高い業界では、管理職の賞与が数百万円単位で上積みされることもあります。特に製造業や商社など輸出入に関わる企業では、景気や為替の影響で賞与額が変動しやすく、同じ部長職でも年収が数百万円単位で異なるケースが見られます。
このように、役職名だけでは給与を判断できず、「企業規模 × 業績」のかけ合わせによって、同じ課長や部長であっても収入が大きく開くのが実態です。転職やキャリアアップを考える際には、企業規模や業績の安定性も視野に入れることが重要になります。
責任範囲と給料のバランス
管理職の給料は、単に役職名だけで決まるのではなく、その人が担う責任範囲の大きさによっても左右されます。例えば課長級でも、部下が数名の小規模チームを率いる場合と、数十人規模の部署を統括する場合とでは、同じ「課長」であっても期待される成果や責任は大きく異なります。こうした違いは、賞与や手当、昇給のスピードに反映されやすいのが特徴です。
また、責任範囲には「部下の人数」だけでなく、担当する業務の幅も含まれます。単にチームの業績を管理するだけでなく、経営層との調整や新規事業の推進を任されるケースでは、より高いスキルと成果が求められるため、給与水準も上がりやすくなります。
一方で、責任が増しても必ずしも給料が比例して上がるとは限りません。特に中小企業では、経営資源が限られているため、部長クラスであっても大企業の課長より給与が低いことも珍しくありません。つまり、「肩書き」と「責任範囲」と「給与」の三者が必ずしも一致するとは限らないのです。
このため、管理職としてキャリアを重ねる際には、自分が置かれている組織で求められる役割と、それに見合った評価・報酬が得られているかを常に確認することが重要です。もし責任と給料のバランスが崩れていると感じる場合には、社内での交渉や転職による環境の見直しが必要になるでしょう。
参照元:企業規模別にみた平均的な賃金は?|生活基盤の安定を図る生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター(2024年)
管理職の給料を上げるために必要なスキル
管理職として給与を上げるためには、単に役職に就くだけでなく、成果を出せるスキルを身につけることが不可欠です。まず重要なのは、リーダーシップとマネジメントスキルです。部下を適切に導き、チーム全体で目標を達成できる能力は、管理職としての基本的な評価指標となります。例えば、プロジェクトの進行管理や目標設定、部下の育成計画を実行することで、チーム全体の成果を上げることができます。
次に、組織戦略や経営戦略への理解も求められます。経営層が描く方向性や目標を正しく理解し、それを現場で実行できる能力は、会社全体の成果に直結します。たとえば、新規事業やコスト削減の計画を自部門で具体化し、数字で結果を出せれば、管理職としての評価は自然と高まります。
さらに、業務改善や効率化のスキルも給与アップには欠かせません。業務プロセスの見直しや無駄の削減、ツール導入による生産性向上など、会社の利益に貢献する具体的な取り組みは、管理職としての価値を高める材料となります。これらのスキルを習得し、実際の業務で成果を出すことが、昇進や評価、そして給与アップの土台になるのです。
転職で給料を上げるためのポイント
管理職として今の会社で成果を出しても、必ずしも十分な給与アップにつながるとは限りません。そのため、転職によって待遇改善を目指す人も少なくありません。転職で給料を上げるには、交渉の進め方や企業選びの基準を理解することが不可欠です。ここでは給与アップを実現するための具体的なポイントを解説します。
転職時の給与交渉術
管理職が転職を考える際、給与交渉は年収アップを実現する重要なステップです。ポイントは単に「もっと高く」と要求するだけでなく、自分の市場価値や実績を根拠として提示することです。厚生労働省や転職支援機関のデータによると、管理職の年収レンジは企業規模や業界で大きく異なるため、交渉材料をしっかり揃えることが成功の鍵になります。
具体的には、以下の点を意識すると効果的です。
- 自己実績の可視化
- 過去のチームや部署の業績、売上貢献度、改善プロジェクトの成果などを数字で示す。
- 例:部下10名のチームで前年比20%の売上増を達成、コスト削減プロジェクトで年間500万円の削減に成功、など。
- 市場価値のリサーチ
- 同業界・同規模の企業における課長・部長クラスの平均給与を把握しておく。
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」や転職エージェントの非公開データを参考に、自分の希望給与が妥当かを検証する。
- 交渉のタイミングと伝え方
- 内定を受けた後、給与条件の提示時に交渉するのが一般的。
- 「自分の経験・実績を考慮すると、この条件であれば即戦力として貢献できる」と前向きに伝えることで、印象を損なわずに条件調整を進められる。
- 総額報酬で考える
- 基本給だけでなく、賞与・手当・退職金・福利厚生なども含めた総額年収で交渉すること。
- 大企業では賞与やインセンティブが年収の大きな割合を占めるため、総額での比較が重要。
管理職の場合、給与交渉は「自分の能力や成果に見合った待遇を正当に評価してもらう場」と捉えることが重要です。数字で示せる成果と市場データをセットで提示することで、交渉成功率は格段に高まります。
給与アップを目指す転職先選び
給与アップを目指して転職する場合、単に求人の提示額だけで判断するのは危険です。管理職の年収は企業文化や業界特性、報酬体系によって大きく左右されるため、転職先選びの際には以下のポイントを意識すると成功率が高まります。
-
-
- 金融、IT、コンサルティング業界は収益性が高く、管理職の給与も高めに設定される傾向があります。
- 一方、飲食や宿泊、サービス業は給与水準が低めで、管理職であっても大幅な年収アップは見込みにくいケースがあります。
-
-
- 従業員1,000人以上の大企業では、給与や賞与の水準が高い傾向があります。
- ベンチャー企業や中小企業でも、業績好調・成長中の企業ではストックオプションやインセンティブで総額報酬を大きく伸ばせる可能性があります。
-
-
- 年功序列型では、管理職であっても給与上昇のスピードが緩やかです。
- 成果主義型の企業では、明確な目標達成で賞与や昇給が大きく反映されるため、給与アップの可能性が高まります。
-
- 組織文化や上司・経営層との相性も重要です。自己の成果や提案を正当に評価してくれる企業であれば、管理職としての価値を最大限給与に反映してもらいやすくなります。
- 逆に、評価が不透明な企業では高いポジションに就いても給与が思ったほど伸びない可能性があります。
このように、給与アップを狙う管理職の転職先選びは、「業界の収益性 × 企業規模 × 評価制度 × 文化的相性」を総合的に判断することが重要です。提示年収だけでなく、賞与・手当・インセンティブなども含めた総額で検討することが、年収アップを現実的に実現するポイントとなります。
転職エージェントの活用方法
管理職が転職を通じて給与アップを目指す場合、転職エージェントは単なる求人紹介の窓口ではなく、給与交渉やキャリア戦略を支援してくれる重要なパートナーとなります。特に管理職は求人数が限られるため、非公開求人や条件の良いポジションを効率的に探すうえで、エージェントの活用が有効です。
具体的な活用ポイントは以下の通りです。
☑︎非公開求人の確認
- 公開求人だけでなく、エージェント経由の非公開求人にアクセス
- 大手企業や外資系企業の部長・部門長クラス案件を優先チェック
☑︎給与交渉の代理を依頼
- 希望年収やインセンティブ条件をエージェントに伝える
- 実績や市場相場をもとに、現実的かつ最適な提示額に調整してもらう
☑︎キャリアプランの相談
- 給与だけでなく、将来の役職や職務範囲を踏まえた戦略を立てる
- エージェントの業界知見や過去事例を参考に、給与と役職のバランスを最適化
☑︎複数エージェントの併用
- 1社だけでなく複数登録し、より多くの非公開求人情報や交渉ノウハウを収集
- 自分の希望条件に合った求人を比較し、給与水準や役職レベルを最適化
☑︎総額年収を意識する
- 基本給だけでなく、賞与・手当・インセンティブを含めた総額で判断
- 年収の構成を理解して交渉材料に活用
このように、管理職が給与アップを目指す場合、転職エージェントの活用は必須と言えるほど有効です。単なる求人紹介にとどまらず、給与交渉やキャリア戦略の相談まで活用することで、転職による年収アップの可能性を最大化できます。
管理職の給料が低い理由と改善策
管理職に昇進しても「思ったほど給料が上がらない」と感じるケースは少なくありません。その背景には、企業の業績や組織構造、評価制度など複数の要因が関わっています。しかし、理由を正しく理解すれば改善の余地はあります。ここでは、管理職の給料が低い典型的な理由と、その解決に向けたキャリア戦略を紹介します。
よくある理由
実際には部下の管理や業務調整に多くの時間を割いているにもかかわらず、企業の就業規則上は「管理職=裁量労働制」とされ、残業代が支給されないケースです。
特に中小企業や古い体制の企業では、形式上の役職だけで給与が固定され、労働時間や業務負荷と給与が比例しないことがあります。
サービス業や飲食・宿泊業など、利益率が低めの業界では、管理職であっても給与水準が抑えられがちです。同じ部長クラスであっても、ITや金融業界と比べると年収差は数百万円単位になることもあり、業界選びが給与に直結します。
- 評価制度が年功序列に偏っている
年功序列型の企業では、役職が上がっても昇給幅が小さく、成果や責任に比例して給与が増えにくい傾向があります。この場合、部下やプロジェクトで大きな成果を出しても、年次や勤続年数に左右されるため、実力に見合った報酬を得られないことがあります。
参照元:管理監督者|名ばかり管理職とならないために企業が知っておくべきポイント – 人事・労務・労働問題の弁護士相談(2023年9月)
キャリアアップ方法
資格取得や成果の数値化を行い、自分の評価を高めることが効果的です。
管理職として給料を上げるためには、単に役職に就くことだけではなく、自分の評価を具体的に高める行動が欠かせません。まず有効なのは、資格取得による専門性の強化です。たとえば、プロジェクトマネジメントのPMPや中小企業診断士、MBAなどの資格を取得することで、業務上の知識や戦略的な能力を裏付けることができ、市場価値が上がります。特に、部門や事業の戦略立案に関わる資格は、昇進や給与評価に直接影響しやすいものです。
また、管理職としての貢献を数字で可視化することも非常に重要です。売上を前年比20%増やした実績や、コスト削減で年間500万円の経費改善、チームの離職率を10%低下させた成果など、数値で示せる業績は、給与交渉や昇進の際に説得力を持ちます。さらに、大規模プロジェクトや新規事業の立ち上げなど、責任の大きい業務を任されることで、役職に見合った報酬や評価を得るチャンスが増えます。
最後に、社内外での評価や認知を高めることも給与アップにつながります。社内では業務改善提案やチーム育成を通して上司や経営層からの信頼を築き、社外では業界団体での活動や講演を通して専門性を示すことで、自身の市場価値をさらに高めることができます。こうした取り組みを積み重ねることで、管理職としての給与や待遇を現実的に引き上げることが可能になります。
参照元:【会社の役職一覧】役割や平均年収、キャリアアップのポイントも解説 | ハイクラス転職ならdoda X(デューダエックス)(2025年3月)
部下との関係・組織内での評価
管理職として給与を上げるためには、自身の役職や実績だけでなく、部下との関係性や組織内での評価も大きく影響します。まず重要なのは、部下の信頼を得るリーダーシップです。単に指示を出すだけではなく、部下一人ひとりの強みや課題を理解し、成長を支援することが求められます。具体的には、定期的な面談やフィードバックを通して目標を共有し、達成をサポートすることが効果的です。
また、組織内での評価を高めるには、チーム全体の成果を上げることが不可欠です。部下の成果を正しく認め、チームとしての目標達成に貢献することで、上司や経営層からの評価も自然と高まります。さらに、自分自身の行動や成果だけでなく、部下の育成やプロジェクト成功への貢献が数字や報告書などで可視化されると、給与や昇進の交渉材料としても有効です。
加えて、組織内での評価を高めるもう一つのポイントは、社内ネットワークの活用と発信力です。部門間の調整や他部署との連携を円滑に行い、自部門の成果だけでなく組織全体への貢献を示すことで、管理職としての価値をさらに高められます。信頼関係の構築、チーム成果の可視化、社内での影響力の拡大を意識することで、管理職としての給与を現実的に引き上げることが可能になります。
管理職としての業務と役割をどう進化させるか
企業を取り巻く環境が変化するなかで、管理職に求められる役割も年々進化しています。従来の「部下を管理する立場」から、組織の成果を高めるリーダーとしての役割がより重視されるようになっています。ここでは、変化する管理職の役割と、それが給料やキャリアにどのような影響を与えるのかを考えていきましょう。
- 役割の変化と給料増加の可能性:近年は「変革リーダー」としての役割が強まり、成果が給与に反映されやすくなっています。
- 部下とのコミュニケーション強化:心理的安全性を高めることで、組織全体の成果も改善。
- 自己成長と会社成長の両立:学び続ける姿勢が昇進・給与アップを後押しします。
管理職の役割は、単に部下を管理する立場から、組織全体の成果を高める変革リーダーとしての役割へと進化しています。近年では、業務改善や新規プロジェクトの成功など、具体的な成果が給与や評価に反映されやすくなっており、管理職としての給料増加の可能性も高まっています。
また、部下とのコミュニケーションを強化し、心理的安全性を確保することでチームのパフォーマンスが向上し、結果として組織全体の成果に結びつきます。さらに、自身のスキルや知識を常に更新し、自己成長を図る姿勢は、会社からの信頼を高め、昇進や給与アップの後押しとなります。
こうした変化を踏まえ、管理職は成果の可視化・部下育成・自己成長の三本柱を意識して行動することで、組織への貢献度を高めながら、自身のキャリアと給与を着実に向上させることが可能です。
まとめ|管理職としての給料アップ戦略
管理職として給与を引き上げるためには、まず自分の役職や給与水準を正確に把握し、業界平均と比較することが重要です。現在の給与が市場価値に見合っているかを理解することで、昇給や転職の判断基準が明確になります。
次に、自身の成果を数値化して可視化することが不可欠です。売上改善やコスト削減、チームのパフォーマンス向上など、具体的な数字で実績を示すことで、上司や経営層からの評価を高め、給与交渉の材料として活用できます。
必要に応じて、転職も視野に入れる戦略も効果的です。業界や企業規模による給与差を踏まえ、転職エージェントを活用して非公開求人や給与交渉のサポートを受けることで、現状より高い報酬を得る可能性が高まります。
さらに、日常業務の中で部下や上司との信頼関係を構築し、成果を積み重ねることも重要です。心理的安全性を高め、チーム全体の成果に貢献することで、組織内での評価も向上し、結果的に給与や昇進に反映されます。
こうした取り組みを総合的に行うことで、管理職としての給与アップは現実的な目標となります。そして、より効率的に次のキャリアを考えたい方には、管理職転職に特化したエージェントの活用が有効です。『sincereed』は管理職向けの求人情報に精通しており、経験や希望に応じた最適な提案や給与交渉のサポートを受けることができます。給与やキャリアの悩みを一人で抱え込まず、信頼できるパートナーとともに次のステップを検討してみてはいかがでしょうか。