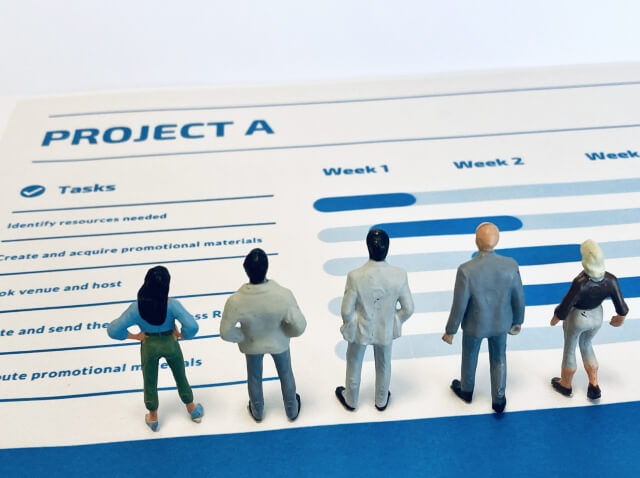JR東海の中途採用・転職難易度、採用倍率は?
JR東海は、日本の主要な鉄道会社の一つで、JRグループの一員です。主に東海道新幹線(東京〜新大阪間)を運営しており、日本の高速鉄道の中心的な存在です。また、在来線では東海地方を中心に、東海道本線や中央本線などを運行しています。
そんなJR東海は転職市場でも非常に人気が高く、「憧れの企業」として多くの求職者が応募するため転職難易度は高めです。特に、募集枠が少ないうえに、即戦力として活躍できる専門スキルを求められるため、しっかりとした対策が必要になります。
※本記事は2025年4月に掲載されました。
※記事中の情報は掲載時点でのWeb情報の公開情報を元に弊社が編集・掲載したものであり、企業の公式見解ではありません。
※組織の詳細や制度等は大きく変更になる可能性があります。ご転職を検討の際は、公式HP等で最新の情報をご確認ください。
そもそもなぜJR東海の中途採用倍率はなぜ高いのか?
倍率が高い理由としては、
(1)応募数が多い
(2)「専門性」が求められる職種が多い
(3)面接の通過率が低い
の3点が挙げられます。
(1)応募数が多い
JR東海は、非常に歴史ある企業です。国鉄(日本国有鉄道)の分割民営化によって誕生し、JRグループの一員として1987年4月1日に設立されました。もともと国鉄が運営していた路線を引き継ぎ、東海道新幹線や東海地方の在来線を中心に事業を展開しています。
創業以来、新幹線の高速化やリニア中央新幹線の開発など、日本の鉄道を進化させ続けているJR東海。JRグループとして「安定した企業で働きたい」と考える転職希望者はもちろん、「新たな挑戦をしていきたい」「日本のインフラを支えたい」など様々な想いを持つ転職者から選ばれる、非常に人気の高い企業です。
(2)「専門性」が求められる職種が多い
JR東海は日本の大動脈を支える東海道新幹線に加え、名古屋・静岡地区を中心に12線区の在来線を運営する、日本のインフラにとって無くてはならない存在です。東海道新幹線の平均遅延時分は運行1列車あたり1.1分、また乗車中のお客さまが死傷される列車事故は開業以降0件と、非常に安定感の高い運行状況を維持しています。また、現在は超電導リニアによる中央新幹線の開業に向けた募集職種も多い状況です。
そのため、特に中央新幹線建設部門においては施工計画の策定、施工管理、土木構造物の設計や工事計画検討、用地取得といった業務において、高い専門性が求められる傾向です。
一方でポテンシャル採用を行っている職種もあります。駅係員などの接客業務をはじめ、車両・機械系統、施設系統、電気・システム系統といった技術系職種においても、社会人経験のある方を広く募集しています。ただ、やはり学生時代の専攻や建設・土木・電気関係の経験や資格など、専門的な知見がある方にとっては有利に働く可能性は高いと言えるでしょう。
(3)面接の通過率が低い
上記2点の通り、人気企業であり、採用ポジションでの求めるスキルから、おのずと面接通過率も低くなっています。JR東海で実現したいことはもちろん、挑戦を恐れずに新たな成長領域に取り組む姿勢や、積極的に新しい知識を吸収し自らの力で行動できる主体性についても書類選考、面接でも評価されるため、同社の具体的なニーズと自分の経験をマッチさせることが重要です。また面接でのこれらのアピールはもちろん論理的思考能力やコミュニケーション能力もポイントとなってきます。
さらになぜJR東海なのか、ポジションによっては同業他社の可能性もあるため、なぜJR東海でなければいけないのかを論理的に述べることがポイントとなっており、その通過率は低くなっています。
どのような対策が必要か?
JR東海への転職では面接対策が重要なポイントとなります。書類においても実際に不採用になっているケースもあるため、ここでは書類、面接と合わせて、どのような対策が必要なのかご紹介していきます。
書類対策
一般的な書き方で問題ありませんが、応募ポジションと親和性のある経験、スキルをアピールしましょう. ます。専門職であればどんな業務内容を経験してきたのか、企画系であれば実績を記載するようにしましょう。転職エージェントに相談し、客観的な意見も交えてブラッシュアップしながら進めると良いかと思います。応募書類の重要なポイントは人事担当者に「会ってみたい」と思ってもらうことです。どんなに人物面がよくてもこの書類選考で落ちてしまっては面接で何も伝えられません。
例えば、担当したプロジェクトの概要、目的、規模、期間、チーム構成などや、自分の役割や責任、具体的な成果や達成した目標、プロジェクトで使用した技術やスキル、ツールなども記載すると良いでしょう。また自分の強みや特長を具体的にアピールすることも必要です。
面接対策
JR東海の面接では、技術力や専門知識はもちろんのこと、「自社のサービスや技術にどれだけ理解があるか」「会社の理念に共感しているか」といったポイントも重視されます。書類選考の倍率が高いため、面接に進めた時点である程度のスキルは認められていますが、最終的に「即戦力になれるかどうか」「社風に合うか」が合否を分ける決め手になります。
企業研究を徹底し、「JR東海」を理解する
JR東海は 「日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する」 という経営理念を掲げており、単なるインフラビジネスではなく、東京~名古屋~大阪という日本の人口・GDPの約6割を占める重要なエリアの輸送を担い、社会経済の発展を支えるビジネスを展開しています。そのため、面接では 「なぜJR東海で働きたいのか?」 を深く聞かれることが多いです。
「鉄道が好きだから」「小さい頃から親しんでいたから」ではなく、なぜ数ある企業の中でなぜJR東海を選んだのかしっかりと経営理念や、JR東海の歴史・事業内容と紐づけて話す必要があります。
これまでの経験がJR東海でどう活かせるかを明確にする
採用では「即戦力」が重視されるため、「あなたのスキルがJR東海でどう活かせるのか?」 を説明できるように準備しましょう。
・職種ごとに求められるスキルを把握する(駅係員などの接客業務や施工管理、設備管理、システム開発など)
・過去の実績を具体的な数字や成果を交えて説明する
・JR東海の事業にどのように貢献できるかを明確にする
といった内容を話せるように予め用意しておきましょう。
協調性・チームワークに対応できる姿勢を示す
「安全・安定輸送」は、運輸、車両・機械、施設、電気・システムの4系統、またさまざまな役職や年齢の社員と一致協力して仕事を行うことにより成り立っています。周囲とのチームワークを大切にしてきたことをアピールしましょう。相手を尊重する基本的なコミュニケーションスキルに加えて、複数の関係者と協力し、成果を出したプロジェクトなどのエピソードがあるとアピール材料になります。
広い視点で物事を捉え、新たなことに「挑戦」する姿勢を示す
東海道新幹線は1964年の開業以来、日本経済の飛躍的な発展を支えてきました。守るだけでなく、「挑戦」する姿勢も大切にしています。「超電導リニアによる中央新幹線計画」という次の「日本」を創る大きなプロジェクトもそのひとつです。企業採用ページの社長メッセージでも「現状に満足せず 常に進化・変革を目指す」という言葉が記載されています。
課題意識を持って何かに挑戦した経験、エピソードはぜひ準備しておきましょう。
さらに、面接の最後に必ず「何か質問がありますか?」と聞かれることが多いので、企業のビジョンや具体的なプロジェクトに関する質問をいくつか準備しておきましょう。これにより、企業に対する関心と理解度をアピールできます。
ただあまりにも応募ポジションとかけ離れた質問は逆効果になります。例えば経営メンバーでない方へ、「今の企業の経営課題と、これからの戦略について伺いたいです」といってもちょっと違いますよね?いわゆるネットから取ってきた質問ではなく、自分自身が面接準備などで疑問に思ったことなど「自分目線」での質問を用意するようにしましょう。
求める人材像
JR東海の中途採用では、即戦力となる技術力・専門知識を持つ人材が求められるのはもちろんのこと、ポテンシャル採用であっても同社の価値観や事業戦略に合った人物であることが重視されます。
採用ページからですが求める人材像を引用します。
JR東海が求める人物像(人事部からのメッセージ)
JR東海は、「日本経済の大動脈である東京~名古屋~大阪間の旅客輸送と社会基盤の発展に貢献すること」を「使命」とし、また同時に自らの「誇り」としています。
1964年の開業以来、約66億人ものお客さまにご利用いただいてきた東海道新幹線は、日本経済の飛躍的な発展を支え、まさに「日本」を形づくる一端を担ってきたといってもよいでしょう。そしてJR東海の果たしていくべきこの「使命」は、新型コロナウイルス感染症の発生により変化した社会環境においても決して変わるものではありません。JR東海がその「使命」を果たすためには、安全確保が何よりも重要であり、そのためには、一人ひとりが責任を果たし、チームワークよく日々の業務を地道に全うしていく必要があります。
一方で、現状にとどまることなく、長期的で広い視野に立って物事を考え、つねにさまざまな「挑戦」を続けることも必要です。「超電導リニアによる中央新幹線計画」という次の「日本」を創る大きなプロジェクトもそのひとつです。
取組みは多岐にわたるわけですから、多彩な人材を必要としており、活躍のフィールドは大きく広がっています。「これからのJR東海、ひいてはこれからの日本を自分たちの手で守り、創っていく。世界の高速鉄道の最先端を切り拓いていく。」というような気概を持っている方にぜひ入社してきてほしいと思います。そこで皆さんには、学生時代に勉強でもスポーツでも何でもよいので、何か目標を設けて、達成しようという努力をしてほしいと思います。入社にあたり、資格や語学能力、大学時代の専攻などを特に重視するということはありません。会社で必要なスキルは入社後にじっくり磨けばよいことです。
それよりもひとりの人間として自分を磨くための貴重な時間である学生時代を有効に過ごしてほしいのです。その過程で自分の長所を伸ばすとともに、つねに「何かを成し遂げよう」というエネルギーに満ちた人になってほしいと思います。
自らの頭で考え、自らの身体で行動する「自律的」な人がひとりでも多くJR東海に飛び込んできてくれることを大いに期待しています。
トップメッセージから紐解くJR東海の求める人材像
JR東海のトップメッセージからも、求める人物像が見えてきます。
【トップメッセージ※一部抜粋】
当社には、自分ひとりで完結するような仕事は多くありません。異なる専門性を持つ社員が協力し、チームワークを発揮してひとつの仕事を達成していきます。使命感を持った人材が、熱意を持って、それぞれにプロらしく、きちんと、チームとして仕事に取り組み、技量を高め、会社をよりよい方向に発展させていく。そのプロセスを通じて、世の中の発展に寄与するという誇りとやりがいを実感する。それがJR東海で働くということだと思います。そして、常に「日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する」という原点に立ち返り、もっと高いレベルでこれを実現できる方法はないかと目標を高く掲げて、チャレンジし続けることが大切だと考えています。
そして当社の使命を果たしていくために最も大切なことは、輸送の安全であるということも忘れてはなりません。経営体力の再強化に取り組むにあたっても、安全輸送を守ることが大前提です。当社には鉄道事業をはじめ、様々な事業がありますが、どの事業領域で働くとしても、この安全輸送の確保が当社の最重要課題であることを改めて認識したうえで、使命の実現に向けて進んでいく必要があります。
会社を強くするためには、技術力を高めたり、設備投資を行ったりと、大切なことはいろいろとありますが、長い期間を考えた時に、やはり一番大事なのは「ヒトの力」だと私は考えています。当社はこれまで、安全を支えるべく、規律正しく、勤勉に、チームワークよく、しっかり仕事をする、そういう人材をきちんと育ててきたという自負があります。一方で世の中は大きく変化しており、この変化に対応するためには、仕事の進め方を常に「進化」させ、「変革」する必要があると考えています。従来のやり方にとらわれず、柔軟に物事を考え、大いに議論を交わし、困難な課題にチャレンジできる、物事をやり遂げる粘り強さがある、そういった人たちに入社をしてきて欲しいと考えています。
JR東海の求める人物像まとめ
以上を紐解くと、JR東海で「こんな人が求められる」という共通点は下記の通りです。
・チームワークよく日々の業務を地道に全うしていける人
・長期的で広い視野に立って物事を考え、つねにさまざまな「挑戦」を続けられる人
・自らの頭で考え、自らの身体で行動する「自律的」な人
・規律正しく、勤勉に、チームワークよく、しっかり仕事をする人
・従来のやり方にとらわれず、柔軟に物事を考え、大いに議論を交わし、困難な課題にチャレンジできる、物事をやり遂げる粘り強さがある人
JR東海の選考フローは?
JR東海の中途採用の選考フローは、書類選考 → 1次面接+適性検査 → 2次面接→(3次面接)→ 内定 という流れが一般的です。職種によっては適性検査の順序が変わったり、適性検査が無い場合もあります。
書類選考
提出した履歴書・職務経歴書をもとに、JR東海の人事部や採用担当者が書類選考を行います。採用担当者は「JR東海の事業にどのように貢献できるか」という視点で応募者を評価します。
適性検査・Webテスト
適性検査のタイミングは、職種によって1次面接時の場合と2次面接時の場合があります(応募職種によっては適性検査はありません)。SPI(総合適性検査)が一般的に使用され、能力や性格の適合度が評価されます。
複数回面接
ここでは主に「基本的な人物評価」と「経験・スキルの確認」が行われます。
「自己紹介・職務経歴を教えてください」
「JR東海に応募した理由は?」
「前職での業務内容と、どのような実績を上げたか?」
「あなたの強み・弱みを教えてください」
「JR東海でどのように貢献できますか?」
のような質問から、
より深掘りした質問が「JR東海の企業文化に合うか」「専門スキルが十分か」がチェックされます。
JR東海 会社概要
| 名称 | 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)
Central Japan Railway Company(JR Central) |
| 設立日 | 1987年4月1日 |
| 事業内容 | 鉄道事業、関連事業 |
| 経営理念と行動指針 | ■経営理念
日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する ■行動指針 ・「安全」最優先の行動 ・「信頼されるサービス」の実践 ・「進化と飛躍」への挑戦 ・「能力と技術」の更なる研鑽 ・「規律ある一体感」の醸成 |
| 本社、その他の事業所 | ■本社
〒450-6101 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 JRセントラルタワーズ ■本社(東京) 〒108-8204 東京都港区港南二丁目1番85号 JR東海品川ビルA棟 ■東海鉄道事業本部 〒453-8520 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目3番4号 JR東海太閤ビル ■静岡支社 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町4番地 ■三重支店 〒514-0009 三重県津市羽所町700番地 アスト津12F ■飯田支店 〒395-0000 長野県飯田市上飯田5356番地 ■新幹線鉄道事業本部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 丸の内中央ビル ■関西支社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号 新大阪阪急ビル 10F ■ワシントン事務所 805 15th Street, NW, Suite810, Washington, DC 20005, U.S.A. ■ロンドン事務所 6th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, U.K. ■シドニー事務所 Suite 5.01A, Level5, 20 Hunter Street, Sydney, NSW 2000, Australia |
経営理念
「日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する」
■「日本の大動脈」とは
当社は東京〜名古屋〜大阪の高速大量旅客輸送を担うことを使命としています。「日本の大動脈」とは、この旅客輸送のことを示しています。この地域は日本の経済や文化の中心として重要な役割を果たしているため、大動脈輸送の停滞は、日本の経済・社会全体の動きの停滞にもつながりかねません。当社は東海道新幹線と中央新幹線により、現在も、そして将来も日本の大動脈輸送を担うという使命を果たし続けていきます。
■「社会基盤」とは
当社は日本の大動脈と一体的に、名古屋・静岡を中心とした地域に根差した在来線運営とこれらの地域を中心とした関連事業展開を行い、人々の生活を支える、より広い意味では「社会基盤」としての使命も担っています。今後も変わりなく在来線網の運営、関連事業の展開にもさらに磨きをかけていきます。
JR東海の事業内容
JR東海は、代表的な東海道新幹線のみならず、多岐にわたる事業を展開している企業です。
新幹線鉄道事業
東海道新幹線は、日本の三大都市圏である東京〜名古屋~大阪を結ぶ大動脈として、1964年の開業以来、半世紀以上にわたって約68億人のお客様にご利用いただき、日本経済の成長を支えてきました。
列車の運転本数は、開業時の1日平均60本から、2019年度には1日平均378本(臨時列車を含む)となり、所要時間についても東京~新大阪間の最速達列車で、開業時の4時間から2時間21分へと短縮し、輸送サービスでの大きな成長を遂げています。
在来線鉄道事業
JR東海は、名古屋・静岡を中心とした地域に根差した在来線運営を日本の大動脈輸送と一体的に行い、人々の生活を支えています。当社が運営する12線区の在来線は、営業キロでは約1,400kmと東海道新幹線の約2.5倍の距離に相当し、通勤・通学をはじめとする日常生活の移動手段、つまり、地域の社会基盤としての使命を果たしています。
営業施策
JR東海では、より多くのお客様に東海道新幹線・在来線をご利用いただけるよう、さまざまな取組みを行っています。
取組みは多岐にわたりますが、主に「東海道新幹線・在来線の利便性向上」、「観光需要の喚起」の二つの取組みに分けられます。
超電導リニアによる中央新幹線
現在日本の大動脈輸送を担う東海道新幹線は、開業から半世紀以上が経過し、大規模改修工事等を講じてきてはいますが、将来の経年劣化による大幅な設備更新に伴う運休等のリスクが存在します。また、日本は地震大国であり、東海道新幹線では耐震補強等の対策を講じてきていますが、大規模地震により長期不通となるなど、大規模災害のリスクも存在します。このため、これらに対する抜本的な備えとして、東海道新幹線とともにその役割を担う中央新幹線について、当社が開発してきた超電導リニアにより可及的速やかに実現して、東海道新幹線と一元的に経営していくこととしています。この中央新幹線計画の完遂に向けて、東海道新幹線と在来線における安全・安定輸送の確保と競争力強化に必要な投資を行うとともに、健全経営と安定配当を堅持し、コストを十分に精査しつつ、柔軟性を発揮しながら着実に取り組みます。
時速500km走行により東京〜名古屋間は最速40分、東京〜大阪間は最速67分となり、中央新幹線と東海道新幹線で結ばれたひとつの巨大都市圏が誕生します。また、中央新幹線の実現は日本が他国にない発展のための強固な基盤を得ることを意味し、経済の活性化だけでなく、豊かで多様な暮らしの実現という新たな可能性をもたらします。
さらに、中央新幹線の開業によって、現行の東海道新幹線のご利用の一部が中央新幹線にシフトするため、東海道新幹線に「ひかり」、「こだま」の増発・増停車など、新しい可能性が生まれます。
グループ事業
JR東海では鉄道事業以外を総称してグループ事業と呼んでいます。沿線都市と移動の価値を高め、人々の豊かな暮らしの実現を目指し、鉄道事業とのシナジーを活かして、幅広いセグメントにおいて事業を展開することで、収益基盤を拡大するとともにグループの総合力を強化しています。保有する多用なアセットを活かし、人の流れを創り、人々の生活を彩るのがJR東海のグループ事業です。
技術開発・技術力強化への取り組み
当社が将来にわたって使命を果たし、発展していくためには、日々の安全の確保に不断に取り組むこと、より快適な輸送サービスを追求していくことに加え、技術開発を通じてこれらを支える基盤となるハードウェアや仕組みを構築していくことが不可欠です。当社では、より一体的かつ総合的に技術的諸課題に取り組むため、2002年に開設した小牧研究施設(愛知県小牧市)において、中長期的な視点から会社施策に資する課題を設定して技術開発の方針を策定し、鉄道事業における安全・安定輸送の確保等につながる技術開発や将来の鉄道システムのさらなる革新を見据えた技術開発を計画的に進めています。
海外展開
海外展開については、2009年7月に設置した「海外高速鉄道プロジェクトC&C(Consulting and Coordination)事業室」を中心に取り組んでいます。C&C事業は、鉄道事業者にしか蓄積しない経験やノウハウを発揮して高速鉄道システムの海外展開を推進する役割を果たしていくことを念頭においています。具体的には、土木構造物・軌道・電力設備・信号設備・車両・運行管理システム・修繕保守等を含めたトータルシステムを海外市場に提案し、プロジェクトが具体化した際には日本の関連企業をコーディネートするとともに、運転・保守に関する各種マニュアルの提供、要員の教育訓練など、高速鉄道が安全・安定的に運行されるための支援とコンサルティングを行います。