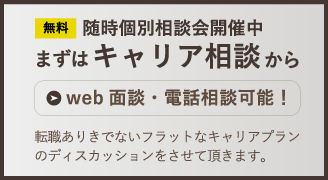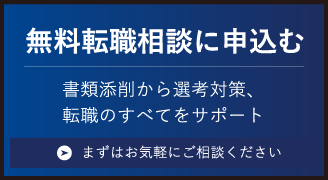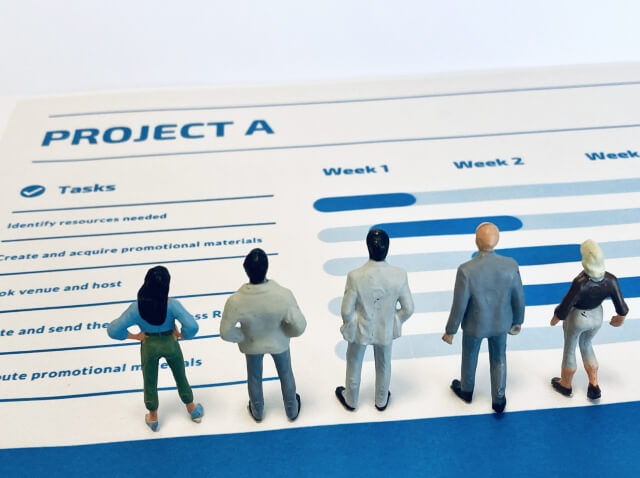富士通は2019年9月に新たな経営方針「IT企業からDX企業への転換」を発表。その実現に向けて、2020年1月にDX専門の新会社「Ridgelines(リッジラインズ)株式会社」を設立するなど、具体的な施策を推進しています。
富士通がDXに注力を始めた背景や、富士通が考えるDXの定義はどのような内容なのか、富士通への転職をお考えの方にとって気になるポイントではないでしょうか。
こちらの記事では、富士通がDX推進に力を入れる背景や、具体的な取り組みなどをご紹介していきます。
※本記事は2024年11月に掲載されました。
※記事中の情報は掲載時点でのWeb情報の公開情報を元に弊社が編集・掲載したものであり、企業の公式見解ではありません。
※組織の詳細や制度等は大きく変更になる可能性があります。ご転職を検討の際は、公式HP等で最新の情報をご確認ください。
富士通へのご転職をお考えの方へ
sincereedの転職支援サービス
大手企業の転職支援に完全特化
専門のコンサルタントが両面型で厚く寄り添うサポート
企業との深いコネクションにより質の高い非公開情報を提供
富士通がDX企業を目指す背景とは?
富士通は1935年に通信機器のメーカーとして事業をスタート。現在では従業員数はグループ全体で約12万人以上、2023年度の売上収益は3兆7560億円と日本を代表する大企業の一つです。そんな富士通がDX企業を目指す背景は何なのでしょうか。
現状への危機感
富士通がDX企業を目指す背景には、近年の環境変化への危機感があるといいます。近年はサブスクリプション(従量課金型)やレベニューシェア(成果報酬型)などのビジネスモデルが登場し、これまで以上に費用対効果が問われる時代になってきました。システム1つ作ることに対しても、これまではかかった労力を重視していましたが、近年はシステムが生み出す価値を重視するように価値体系も変わってきています。このような環境の変化を受けて、富士通も今までのように既存システムの保守・メンテナンスなどに予算をかける「守りの投資」よりも、売上高の向上に繋がる「攻めのIT投資」への提案にシフトしていく必要があると考えています。
ビジネスモデルの変革が必要不可欠
また富士通はDXを通して、自社のビジネスモデルそのものを変えなければならないと考えています。富士通が2020年1月に設立したDX専門の新会社「Ridgelines(リッジラインズ)株式会社」の社長である今井氏は、富士通はある時期に国内のIT企業として急成長を遂げたものの、そこから10年以上にわたって伸び悩んでいたと捉えています。
そして外部のコンサルタントとして、その要因がどこにあるのかを考えたとき、そもそも富士通に限らず日本のIT産業のビジネスモデルが寿命を迎えているのではないかと強く感じたそうです。「変わり切れない」富士通を変えるべくRidgelinesの代表に就任した今井氏や、富士通の最高DX責任者である福田氏を筆頭に、富士通の全社変革が推進されています。
富士通の全社DXプロジェクト「フジトラ」とは?
富士通では2020年よりフジトラ(Fujitsu Transformation:IT企業からDX企業へ生まれ変わるための変革プロジェクト)を開始しています。新事業の創出、既存事業の収益性強化、業務プロセスの効率化、人事制度や働く環境などが変革の対象となります。
自社の変革を進める中で得たノウハウはサービスやソリューションに反映し、顧客に提供する見通しです。
グローバルで12万人を超える社内を変革するのは容易ではありませんが、社長自らがリードするトップダウンと全員参加型のボトムアップ、両輪によって粘り強く実践する中で日本型DX推進の形が見えてきつつあります。
ここではフジトラの設立背景や、目指すゴールなどをご紹介していきます。
フジトラの設立背景
富士通がお客様や社会のDXを支える企業となるためには、富士通自身が変革する必要があり、その姿をお客様や社会へ示し、リファレンスとなることで、社会に貢献していくことが重要だと考えました。そのような背景から「フジトラ」のプロジェクトはスタートしています。
フジトラの中核を成すのは、「富士通をよりよくする」ミッションと志を持って集まった約60名のDX Officerです。DX Officerはグループのすべての主要部門やリージョンから参加しているため、部門を横断した取り組みを得意とするフォーメーションであることが特徴です。変革には組織の壁の打破が必須だからです。
フジトラが目指すゴール
富士通が最大の課題と置いているのは、変革マインドの浸透です。「挑戦する文化」「(挑戦して)失敗してもいい」という文化を醸成しなければならないと考えています。以前の富士通に浸透していた「変わらない」姿勢や組織文化に一石を投じてきたのが、フジトラです。
「フジトラ」には「経営のリーダーシップ」、「現場が主役 全員参加」、「カルチャー変革」の3つのキーポイントとなる主軸があります。経営と現場が一体となり、全社・全員参加で取り組む自己変革プロジェクトとして活動を推進しており、目指すゴールは「フジトラ」がなくても変革を起こし続け「フジトラが解散すること!」として位置づけられています。
フジトラのDX推進における4つの重要な柱
DXというと一般的には業務のデジタル化などを想像されるかもしれませんが、「フジトラ」では、パーパスを中心に人・組織・カルチャーの変革(EX)、オペレーションの変革(OX)、マネジメントの変革(MX)、事業の変革(CX)の4つの柱でDXを推進していきます。富士通が掲げるパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」の理想像へ近づくため、変革を多面的にとらえ、試行錯誤を続けながら実践しています。
特に人・組織・カルチャーの変革(EX)に関してはDX推進当初から重要視してきました。現在の時田社長が外部取締役主導の指名委員会で選任された富士通史上初の社長だったり、経営陣の3分の1が多様なバックグラウンドを持ったキャリア入社者だったりと、従来とは違った視点や価値観を取り入れており、「今までと同じではまずい」という空気が醸成されつつあるようです。
フジトラ ステートメント
「フジトラ」では発足当初から自分たちのありたいカルチャーや行動様式をステートメントとして定め、活動を行ってきました。
第8代社長小林大祐の「ともかくやってみよう」といった富士通自身のDNAとも言える言葉から、「パーパスを胸に」「最高のエクスペリエンスを」といった「フジトラ」が目指す姿まで、9つの項目から構成されています。
| パーパスを胸に |
Purpose Driven |
| オープンなコラボレーション |
Open Collaboration |
| 私らしい働き方で |
Human centric way to work |
| 最高のエクスペリエンスを |
Customer experience |
| データを武器に |
Data-driven decision making |
| ともかくやってみよう |
Giving it a try |
| 全員参加で |
Inclusion&Ownership |
| 未来をリ・デザイン |
Redesign future |
| ファーストペンギンとして |
First penguin |
富士通の全社DXプロジェクト「フジトラ」具体的な取り組み事例
「フジトラ」発足から4年が経過した現在では、約150もの変革テーマが誕生しています。この変革テーマは3か月を1サイクルとして、役員のステアリングコミッティや各組織のDX推進者同士の交流・対話、全社参加型のイベントなどを実施し、様々な意見を元に試行錯誤を重ね、テーマの追加やアップデートを継続的に行っています。
このような活動からうまく進んだテーマの実践知をフレームワークとして形式知化し、様々な組織に横展開してきました。現在では社外にも展開され、お客様が実践される事例も出てきました。
ここでは150のテーマの中から、代表的なものをご紹介します。
One Fujitsuプログラム
会社や経営の仕組みを未来志向に最適化するために主要プロジェクトとして立ち上げたのがOne Fujitsuプログラムです。ITを活用し、富士通グループ全体で「戦略」「組織」「制度ルール」「データ」「業務プロセス」「アプリケーション」「インフラ」の7点を標準化するという計画です。
これにより、1機能1システムを実現するとともに、標準化されたデータで「富士通のデジタルツイン」を作成することで、データドリブン型経営への全社的なシフトを目指します。
新規事業創出プログラムFujitsu Innovation Circuit
Fujitsu Innovation Circuit(以下、FIC)は、富士通グループにおける「アントレプレナーシップ人材の育成と、新規事業の創出を目指すプログラム」です。
※アントレプレナーシップ…創造的でオープンマインドな思考や革新的な問題解決力、挑戦するマインド(起業家的思考)を身につけた人材
FIC立ち上げの起点は「今の富士通は、失敗を恐れるあまりイノベーティブな風土とは程遠い状態にあるのではないか」という課題感でした。誰もが挑戦の舞台に立てる、挑戦が当たり前の富士通を作りたいという想いのもとに立ち上がったのがFICです。
FICは大きく二つのプログラムで構成されており、方法論やマインドセットを身に付ける学びの場(Ignition)、新規事業実践の場(Challenge)です。
Ignitionでは、起業家教育全米No.1のバブソン大学で教鞭をとるアントレプレナーシップ准教授 山川 恭弘氏による3か月にも及ぶ全11回のワークショップ(Academy)をはじめ、社外プロフェッショナルからの方法論やマインドセットを学ぶコンテンツを多数展開。これまで国内外2500名以上の富士通グループ社員がこのプログラムに参加しました。
また実践プログラムでは、審査に通過した人だけが社内起業家として通常業務から離れて新規事業創出に100%専念し、社外プロフェッショナルや社内有識者の支援を受けながら最大6か月で本格投資に値する事業を作り上げていきます。
2024年10月時点で145チームがChallengeへの参加審査を受けて、35チームが審査を通過し活動してきました。Challenge卒業生により様々な事業も創出されています。
VOICEプログラム(VOICE)
VOICEプログラム(VOICE)は、従業員や顧客の意見を収集するための、全社員参加型プログラムです。特定テーマに関する意見を収集して、業務データなどと組み合わせることで「なぜその事象が起きたのか(理由・背景)を正しく理解できるため、課題発見などのインサイトを獲得するために用います。
回答時に従業員の所属や属性なども併せて収集されるため、データ集計の手間も省力化が可能です。既にVOICEは、新型コロナ感染症によるリモートワークの業務への影響や働き方、生産性についての従業員の意見を収集し、その回答を分析する試みを行なっています。
Work Life Shift
富士通ではアフターコロナを見据えて、オフィスでのリアルなコミュニケーションの効果的な活用を組み合わせた真のハイブリッドワークやLifeのさらなる充実、ウェルビーイングの実現などを目指し、2021年10月から「Work Life Shift 2.0」をスタートさせました。
「仕事」と「生活」をトータルにシフトするため、実際の働き方を働き方を同社のAI「Zinrai」で分析。どんな仕事にどれだけ時間を使っているのかをセンシングしてAIが分析し、分かりやすく従業員へ示すことで、自分自身の仕事の進め方を見直したり、上司とのコミュニケーションに生かしたり、特定の社員に業務が集中しないよう分散させています。バラバラで働く分、見えなくなった仕事の実態をデータで可視化していきました。
取り組みの結果、テレワーク継続率平均80%、通勤時間の減少が1人当たり平均30時間(月)、単身赴任の解消など遠隔勤務の活用約1700名、社外サテライトオフィスの利用約9000名(月)など、様々な変化をもたらしています。※2022年1月28日現在
社内SNS活性化/コミュニケーション
社内SNSの活用は変革のプラットフォームと位置づけていましたが、2020年のプロジェクト開始当初は使用率が低く、閑古鳥が鳴いている状況でした。しかし、経営陣も積極的に参画することで、現在では社員の8割以上がアクティブユーザーで、1万を超えるコミュニティが生まれるほど活用されるようになっています。
DXに関する新会社設立や出資
富士通は上記の通り自社内での取り組みはもちろん、DXに関わる子会社の設立や出資も行っています。
Ridgelines(リッジラインズ)株式会社
2020年4月に富士通の完全子会社として誕生しました。Ridgelinezはコンサルティングを事業の中枢に据え、顧客企業のDXのニーズを聞き出し、新たな事業戦略や業務プロセスの策定を支援。策定した戦略に基づいて、人工知能(AI)やあらゆるモノがネットにつながる「IoT」などのデジタル技術を駆使した解決策や試作品も提案しています。またお客様のDXを支援するのはもちろん、富士通自身の変革も支援します。
株式会社DUCNET
ファナック株式会社、NTTコミュニケ―ションズ株式会社とともに、製造業のDXを支援する場をクラウドサービスとして提供する新会社「株式会社DUCNET(ディーユーシーネット)」を2020年11月に設立しました。
工作機械業界のDXを加速させるべく、「デジタルユーティリティクラウド」を利用する各企業のさらなるものづくり力の強化に貢献すること、並びに機械メーカーや機械ユーザー、商社、ITベンダーなどの参加各社が、サービス提供者でありサービス利用者になれるようなエコシステムの実現を目指します。
富士通へのご転職をお考えの方へ
富士通への転職難易度は非常に高く、十分な面接対策なしでは内定獲得は難しいと言えます。
弊社sincereedだからこそわかる選考対策、さらには入社後の早期活躍方法についても多くのアドバイス、サポートが可能となっております。
富士通への転職にご興味のある方は、まずは一度ご相談いただければ幸いです。
富士通へのご転職をお考えの方へ
sincereedの転職支援サービス
大手企業の転職支援に完全特化
専門のコンサルタントが両面型で厚く寄り添うサポート
企業との深いコネクションにより質の高い非公開情報を提供